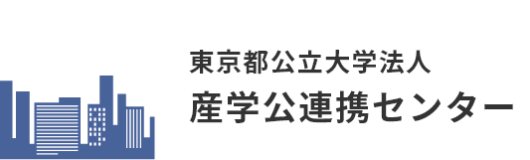お知らせ
Miyacology Connect 8号
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
総合研究推進機構ニュースレター
◆◆ Miyacology Connect ◆◆
8号(2025年8月18日発行)
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ INDEX
┣【1】公募情報
┃ │ 1)(予告)ERCA 環境研究総合推進費
┃ └ 2) JST 日ASEAN科学技術・イノベーション協働連携事業(NEXUS)
┃ 日本-タイ共同研究「バイオテクノロジー」
┣【2】審議会情報:(研究費部会)科研費 学術変革研究種目群のあり方の検討状況
┗【3】研究FDコラム: 科研費 基盤研究に「国際性」の評価が加わりました
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】公募情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※ 公募情報の【研究推進課〆切】について
応募にあたり「文書番号が必要」「公印押印が必要」「機関申請(機関の長が
代表として応募する)」「機関承認が必要(e-Rad上での承認を含む)」となる
場合、研究推進課〆切が設定されます。研究推進課〆切の目安は以下の通りです。
・ 要文書番号、要公印、要機関申請・機関承認:公募〆切の5営業日前
・ 要文書番号、要機関申請・機関承認:公募〆切の5営業日前
・ 要文書番号:公募〆切の3営業日前
・ 要機関申請・機関承認:公募〆切の3営業日前
別途部局〆切が設定される場合がありますので、所属部局事務担当にご確認を
お願いします。
※ 総合研究推進機構HPにて民間財団助成金等の公募情報を掲載しています。
https://research-miyacology.tmu.ac.jp/fundingdb/
───────────────────────
1) (予告)ERCA 環境研究総合推進費
───────────────────────
【公募サイト】https://www.erca.go.jp/suishinhi/koubo/index.html
【公募説明会】令和7年9月12日(金)10:30~18:00(オンライン開催)
【募集領域】「統合領域」「気候変動領域」「資源循環領域」「自然共生領域」
「安全確保領域」
【応募方法】e-Radによる応募
【公募期間】令和7年9月8日(月)~令和7年10月10日(金)
───────────────────────
2) JST 日ASEAN科学技術・イノベーション協働連携事業(NEXUS)
日本-タイ共同研究「バイオテクノロジー」
───────────────────────
【公募サイト】https://www.jst.go.jp/aspire/nexus/koubo/country/thailand.html
【募集領域】バイオテクノロジー
1. クリーンエネルギーと脱炭素のためのゲノム工学技術
2. 代替食品や機能性分子のための精密発酵技術
3. プラネタリーヘルスのための微生物群衆制御技術
【応募方法】
(日本側研究者)e-Radからの申請
(タイ側研究者)申請システムNRIISを通じて申請
【提出〆切】2026年9月26日(金)14時(日本時間)
【機関承認の要否】要(要公印または文書番号)
【研究推進課〆切】9月19日(金)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】審議会情報:(研究費部会)学術変革研究種目群のあり方の検討状況
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今期の研究費部会における、科研費 学術変革研究種目群(「挑戦的研究」「学術
変革領域研究」)の拡充・改善にかかる検討状況です。
若手研究者の振興・融合領域研究へのチャレンジを促進する支援の一体改革の推進
として、以下の4つの観点から検討が進められています。このうち(1)、(4)が
今年度中(~令和8年3月)の検討事項となっています。
(1) 【長期間にわたる安定的な資金の提供】
「挑戦的研究(萌芽)」から「挑戦的研究(開拓)」への接続強化のための具体的
方法として、応募書類・審査の観点の見直しや応募機会の拡大について検討されて
います。具体的には以下の2点です。
・ 「挑戦的研究(開拓)」への応募にあたり、「挑戦的研究(萌芽)」の成果の
記載を求め、その発展性を審査の観点に追加
・ 若手研究者を対象に「挑戦的研究(萌芽)から」「挑戦的研究(開拓)」への
最終年度前年度応募を認める
(2)【応募課題の学際性に配慮した審査体制の採用】
挑戦性に関するクリアなメッセージの発信や、審査区分表の見直し、複数の審査
区分での審査について、具体的な審査方法や実現可能性・要否も含めて今後検討
することになっています。
・ 「挑戦性」についてより明確にし、応募者および審査委員に十分理解して
もらうことが必要であるという観点から、「挑戦性」に関する複数の観点の
例などを示す
・ 審査委員の審査負担の軽減の観点から、「挑戦的研究(開拓)」についても
二段階書面審査を採用する
・ 複数の審査区分による審査の導入
(3)【採択率の向上の必要性】
若手研究者の挑戦の機会創出を支援するという観点から、若手研究者を対象とする
優先枠(仮称)の設定や、重複応募制限の緩和が検討されています。
・ 「挑戦的研究(萌芽)」において若手支援優先枠(仮称)を設定
・ 若手研究者に限定して「挑戦的研究(萌芽)」と「基盤研究(C)」間の重複
応募制限を緩和
(4)【学術変革研究種目群のあり方】
新領域の開拓、国際プレゼンスの向上を図るという観点から、「学術変革領域研究(B)」
において、「挑戦的研究」やJST所管の「創発的研究支援事業」からの接続強化や、
国際性評価の導入などが検討されています。
・ 「創発的研究支援事業」の採択時年齢等を踏まえた年齢制限(45歳以下)の見直し
・ 「基盤研究」で導入した国際性の視点を審査に取り込むこと
このほか、研究初期の段階から新興・融合領域研究へのチャレンジを促すため、
「挑戦的研究」への導入と合わせて、「若手研究」においても複数の審査区分への
応募方法について検討されています。
(ご参考)第13期研究費部会(第2回)会議資料
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/053/siryo/mext_00002.html
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】研究FDコラム: 科研費 基盤研究に「国際性」の評価が加わりました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昨年度(令和7年度公募)から、基盤研究(A)(B)(C)の審査項目に「国際性」の
評定要素(審査の観点)が新たに追加されました。
これは「海外連携研究(旧:国際共同研究強化(B))」の公募停止に伴う措置で、
応募額に応じた適切な研究費配分を目指すものです。
研究計画調書では、提案する研究がどのような国際性を持つかを記載する必要が
あります。国際的な競争力や波及効果が高いと評価された研究には、重点的に
研究費が配分される仕組みです。
さらに、若手研究者による国際性の高い研究課題を追加的に採択する
「国際・若手支援強化枠」も新設されました。
審査の手引きでは、国際性に関する評定要素は4段階での絶対評価が行われ、
たとえば以下のような観点から評価されます。
・ 将来的に世界の研究をけん引するか(先導性)
・ 協同を通じて世界の研究の発展に貢献するか(共同性)
・ 我が国独自の研究としての高い価値を創出するか(独自性) 等
また、これらに限らず、当該審査区分の特性に応じて、「国際性」が評価される点も、
留意すべきポイントです。
本学の昨年度実績では、基盤研究の平均的な充足率が約72%だった一方で、
複数の課題では充足率が92~99%(基盤研究(A)(B))と非常に高い水準でした。
これは国際性が高く評価されたことにより、研究費が重点的に配分されたものと
うかがえます。
充足率が高い調書を拝見したところ、以下のような順序での書き方が見られました。
(1) 関連分野の国際的な研究動向とその課題。
(2) 当該研究課題を進めることにより、(1)の課題に対しどのように影響を与え、
どう世界をリードする研究を行うことが期待されるのか。
または、(1)の課題に対し、当該研究課題での独自のアプローチによって、どの
ように課題解決に貢献できるのか。
単なる海外連携にとどまらず、研究の先導性や独自性をどう世界に示すかという視点が
問われている印象です。
一方、本項目の記載ボリュームとしては1/3ページに満たない程度であり、この箇所の
記述だけで国際性を絶対評価するのにはやや難があるとも考えられます。申請書全体を
通じて、研究の本質的な価値や波及力を問う視点での説明が求められそうです。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
総合研究推進機構URAは外部資金獲得支援、申請書作成支援を実施しています。
支援のご希望はお問い合わせ先まで。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
配信登録・停止はこちら:https://forms.office.com/r/mUUhqELecx
お問い合わせ:ura-shien [at] jmj.tmu.ac.jp
発行:総合研究推進機構(研究推進課)
https://research-miyacology.tmu.ac.jp/
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━