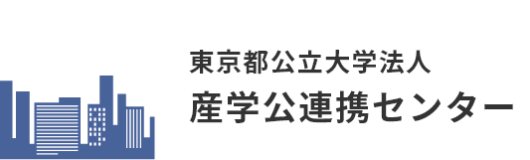耳紋で犯罪捜査を変える─指紋に続く新たな個人識別技術への挑戦
全トピックスで【Web限定あり】
人の耳の形は指紋と同じように一人ひとり異なり、個人を特定できる生体情報として注目されています。システムデザイン研究科の西内信之先生は、犯罪現場に残された「耳紋(じもん)」を高精度で照合できるデータベース生成システムを開発。ヨーロッパでは既に犯罪捜査に活用されている耳紋識別技術を、最新の画像処理と機械学習で進化させ、より確実な個人認証の実現を目指しています。

西内 信之 教授
NISHIUCHI Nobuyuki
システムデザイン研究科 情報科学域
横浜国立大学大学院にて博士(工学)取得。2020 年より東京都立大学システムデザイン学部情報科学科教授、同大学院システムデザイン研究科情報科学域を兼担し、現在に至る。専門分野は生体計測、ヒューマンインタフェース、ユーザビリティ、ユーザエクスペリエンス、バイオメトリクス。
押し付ける力で変わる耳紋
私が現在取り組んでいるのは、「耳紋データベース生成システム」の開発です。耳紋とは、人が壁やガラスに耳を押し付けた際に残る跡のことで、指紋と同様に個人を特定できる生体情報として、オランダやイギリス、スイス、ポーランドなどヨーロッパ諸国では実際に犯罪捜査で活用されています。
日本ではまだ馴染みがありませんが、実は海外では長い歴史があります。例えば、空き巣が隣の部屋に人がいるかどうかを確認するために壁や窓に耳を当てるといった行為で、犯罪現場に耳紋が残ることがあるのです。手袋をしていて指紋が採取できない場合でも、耳紋があれば重要な手がかりになります。
しかし従来の手法には大きな問題がありました。耳は柔らかい軟骨でできているため、押し付ける力の強さによって跡の形が大きく変化してしまうのです。犯罪現場に残された耳紋がどの程度の力で押し付けられたものかは分からないため、容疑者から採取した耳紋との照合が困難で、識別率のさらなる向上に向けた改善が必要でした。
【Web限定】この研究を始めるきっかけとなったのは、ポーランドの大学との共同研究でした。現地の警察では、バネばかりのような装置と転写シートを使って手作業で段階的に押し付け力を変えながら耳紋を採取していました。しかし、この方法では数パターンの押し付け力(実際には3種類)でしか測定できず、現場の耳紋との完全な照合は困難でした。そこで私は、「連続的に全ての押し付け力レベルでの耳紋を一度に取得できないか」という発想に至ったのです。
-
従来の「手で転写シートを耳に押し付けて耳紋を採取する装置」(研究室で試作)
-
転写シート
私のシステムでは高速度カメラとロードセル(荷重センサー)を組み合わせ、耳を押し付けている間の連続的な耳紋の変化を1秒間に125枚の画像として記録します。これにより、0.1ニュートンから目標値まで、あらゆる押し付け力レベルでの耳紋画像を一度の測定で取得できるのです。現場に残された耳紋がどの押し付け力で形成されたものであっても、データベース内の対応する押し付け力レベルの画像と照合できるため、識別精度の大幅な向上が期待されます。
 アクリルブロックに耳を押し付けて耳紋を撮影
アクリルブロックに耳を押し付けて耳紋を撮影
技術的な核心は、耳紋採取用の透明なアクリルブロックを使った光学システムと、耳の押し付け力を同時に測定できるロードセルとの組み合わせにあります。台形断面の特殊なプリズムに下から光を照射し、耳が接触している部分だけが乱反射して光って見える仕組みです。接触していない部分は見えないため、耳紋の形状を正確に捉えることができます。この原理自体は指紋採取技術の応用ですが、耳紋用に大型化し、さらに耳の押し付け力と耳紋を同時に連続測定できる点が独自の技術です。
装置開発では多くの試行錯誤がありました。当初は水平に耳を押し付ける方式でしたが、使用者にとって強い力で押し付けることが困難なつらい姿勢だったのです。最終的に、立った状態で耳を押し付けられる自然な姿勢に変更し、使いやすさが大幅に向上しました。また、厚いアクリルブロックの製作や、光学系とセンサの精密な組み合わせなど、技術的課題の解決には約3年の開発期間を要しました。
VRから読み取る「楽しさ」
【Web限定】耳紋システムと並行して取り組んでいるのが、VR(バーチャルリアリティ)における体験評価の自動化です。私の研究の根底には生体計測という共通基盤があり、人間とコンピュータの関係をより良くするヒューマンコンピュータインタラクション(HCI)という分野から発展してきました。
従来の研究分野では「ユーザビリティ」、つまり「使いやすさ」が重視されていましたが、近年は「ユーザエクスペリエンス」、すなわち体験全体の質が注目されています。物を作るのではなく体験を作る時代において、その体験をどう評価するかが重要な課題となっているのです。
 市販のVRヘッドセットがそのまま研究に使えると西内教授
市販のVRヘッドセットがそのまま研究に使えると西内教授
VRヘッドセットには元々、目の動きや顔の表情、体の動きを検知するセンサが搭載されています。私はこれらのセンサから取得できるデータを機械学習にかけることで、ユーザがそのVRコンテンツを「楽しいと感じているか」を自動判定できるシステムを開発中です。
このシステムの興味深い点は、リアルタイムでの評価が可能なことです。
例えば、ジェットコースターのVR映像を体験している最中に、ユーザがVR酔いで気分が悪くなったことを検知すれば、自動的にスピードを落としたり、没入感を調整したりできます。また、美術館の展示で来館者が退屈そうにしていることが分かれば、展示の順序を変更したり、説明の方法を調整したりすることも可能になるでしょう。
来年度からはより大規模な研究予算を得て、実用化に向けた開発を進める予定です。3年後には実際にゲーム会社などで活用できる試作品の完成を目標としています。

ヘッドマウントディスプレイから見られる映像の切り取り画像。
この動画を見た人が何を感じているか自動判定できる日が近づいている
耳紋による個人識別が拓く新たな科学捜査
これらの技術が社会に実装されると、どのような変化が起こるかというと、まず犯罪捜査の精度向上が期待されます。
現在、日本の警察では指紋や顔のデータベースが構築されており、これらは犯罪捜査に大きく貢献していますが、耳紋システムも同様に、各警察関係機関に設置されることで、より幅広い生体情報による個人識別が可能になるでしょう。
また、耳紋は成人になるとほとんど変化しないという特徴があります。指紋は怪我や職業による磨耗で変化することがありますが、耳は比較的保護されているため、長期間にわたって安定した個人識別が可能です。さらに、他の生体認証技術と組み合わせることで、犯罪の早期解決や再犯防止に寄与できると考えています。
【Web限定】一方、VR体験評価技術は、コンテンツ産業に革命をもたらすかもしれません。映画、ゲーム、教育コンテンツなど、あらゆる体験型メディアで「本当に面白いのか」「どこを改善すべきか」が科学的に分析できるようになります。これは制作者の勘や経験に頼っていた従来の手法から、データドリブンなコンテンツ開発への転換を意味します。
例えば、映画の試写会でリアルタイムに観客の反応を分析し、つまらないと感じられているシーンを特定できれば、編集段階で修正することが可能になります。ゲーム開発では、プレイヤーがどの場面で最も楽しんでいるか、どこで退屈しているかを把握し、ゲームバランスの調整に活かすことができるでしょう。
安全で豊かな社会への架け橋
しかし、実用化には依然としていくつかの課題が残されています。
【Web限定】耳紋システムの重要な課題の一つは、日本における法的位置づけに関する問題です。ヨーロッパでは犯罪捜査に活用されている実績があるものの、日本ではまだ注目度が低く、制度的な整備・運用実績が明確には確認できていません。指紋認証が法的に確立されるまでにも長い時間がかかりましたが、耳紋についても同様に社会的・法的な整備には時間を要すると考えられます。
まずは学術的な実績を積み重ね、技術の有効性を証明することが重要です。現在、約30人分の耳紋データベースを構築しており、今後はより大規模なデータセットを作成し、認証精度の向上に向けて、様々な照合アルゴリズムを検討していく予定です。
 現在は身長測定器ほどの大きさ。小型化が実用化の鍵になる。
現在は身長測定器ほどの大きさ。小型化が実用化の鍵になる。
とりわけ、装置の小型化とコストの抑制は、実運用へ近づくための重要な要件です。現在の試作機は研究レベルのもので、警察関係機関に実際に配備するには、より高精度かつ安価で扱いやすい装置への改良が必要です。企業との共同開発を通じて、メンテナンスしやすく現場で使いやすいシステムに発展させていきます。
【Web限定】VR 評価システムについては、プライバシーや倫理的な配慮が欠かせません。ユーザの生体データを取得・分析することについて、適切な同意の仕組みや法的整備が必要でしょう。特に、評価結果がユーザにとって不利益にならないよう、データの取り扱いには細心の注意が必要です。
また、個人差への対応も課題です。同じコンテンツに対する反応は、文化的背景、年齢、性格などによって大きく異なります。より多様なデータを蓄積し、個人差を考慮した評価アルゴリズムの開発が必要でしょう。
今後は、ポーランドの大学との国際共同研究を通じて海外での実績を積み重ねるとともに、日本の警察関係機関との連携も模索していきます。また、企業との共同開発により、実用的なシステムへの発展を目指します。生体計測技術という私の専門分野を基盤に、人工知能や機械学習といった最新技術を組み合わせることで、社会の安全を向上させる研究を続けていきたいと考えています。
技術が社会に受け入れられるためには、単に高性能であるだけでは十分ではありません。使う人の立場に立って、本当に役立つシステムを作り上げること。そして、技術と社会の間に立って、両者を繋ぐ架け橋の役割を果たすこと。それが研究者としての私の使命だと感じています。