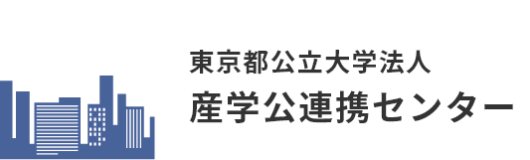植物の可能性を拡げる「顕微授精法」ー環境変化に強い作物開発への挑戦
-
学内にある栽培施設。異種ゲノム混ざり具合により高さの異なるトウモロコシコムギが生育している

岡本 龍史 教授
OKAMOTO Takashi
理学研究科 生命科学専攻
国際基督教大学教養学部理学科卒業後、東京都立大学大学院理学研究科生物学専攻にて理学博士号を取得。その後、同研究科にて助手を務めながら、日本学術振興会海外特別研究員としてドイツで顕微授精法を研究。帰国後の2005 年に首都大学東京理工学研究科准教授、2015年より現職。専門は植物発生学。
植物の受精過程を解き明かす
【Web限定】私は現在、植物の発生学や生理学を専門に、植物がどのように受精し、その後どのように発生していくのかを研究しています。植物の受精は、花粉が雌しべの柱頭に付着し、そこから伸びる花粉管が胚珠(胚のう)に到達して受精が起こるという流れが一般的です。このプロセスは植物体内で進行するため、受精のメカニズムを直接観察するのは非常に困難です。
そこで私たちの研究室では、植物の卵細胞と精細胞を体外に取り出して受精させる「顕微授精法」を採用しています。この方法では、まず卵細胞と精細胞を電極の間に配置し、交流電流下で細胞を一直線に整列させます。次に直流のパルス電流をかけることで、卵細胞と精細胞が接着している細胞膜領域に微細な穴が開き、細胞同士の融合が進行します。こうして人工的に作られた受精卵は細胞分裂を開始し、最終的には植物体へと成長していきます。この技術の特筆すべき点は、同種の配偶子だけでなく、遠縁の配偶子も自由に融合することができるので、任意の種の組み合わせの受精卵を作ることができることです。
この技術により、受精から初期発生までのプロセスを詳細に観察できるようになっただけでなく、これまで自然界では交雑できなかった異なる種の植物同士を掛け合わせ、新たな特性を持つ植物(細胞質雑種植物)を創出することも可能になりました。世界的に見ても、この顕微授精法を用いた研究を続けているのは、私たちの研究室と中国の1グループのみで、私が学んだドイツの系譜を継ぐ2つの流れだけが残っています。植物を一年中育て、配偶子を安定して取れる状態を保ち、この研究系を途切れさせずに継承し、さらに発展させる体制を整えていることが、私たちの研究室の強みです。

異種交配の壁を超え、気候変動に耐える次世代作物をつくる
【Web限定】私は昨年度まで、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のムーンショット型研究開発事業「遺伝子最適化・超遠縁ハイブリッド・微生物共生の統合で生み出す次世代CO₂資源化植物の開発」プロジェクトに参画し、研究を行っていました。
このプロジェクトには大きく分けて2つの目的があります。ひとつは、植物の受精メカニズムをより深く理解すること。もうひとつは、顕微授精法を活用し、自然界では交配が難しい異種植物間で雑種を作り、新たな特性を持つ植物を開発することです。現在は特に後者、すなわち異種間交雑の研究に力を入れています。
自然界では、異なる種の植物同士は「生殖的隔離」によって受精が起こらないのが一般的です。しかし、私たちは電気融合を用いた顕微授精技術によって、この壁を乗り越えることに成功しつつあります。例えば、イネ卵細胞、コムギ卵細胞、コムギ精細胞の組み合わせで、またはコムギとトウモロコシ、あるいはパールミレットとの交雑も進めており、それによって得られる雑種を「細胞質雑種」と呼んでいます。
なかでも、トウモロコシ由来のミトコンドリアを持つコムギの開発に注目しています。イネやコムギは「C3植物」として温帯域および冷涼な気候に適した光合成経路を持ちますが、トウモロコシやパールミレットは「C4植物」として高温・乾燥環境でも高い光合成効率を保つことができます。ミトコンドリアは単なるエネルギー供給装置ではなく、光や温度などの環境変化を感知し、その情報を細胞核に伝える「環境センサー」としても機能しています。このため、C4植物であるトウモロコシのミトコンドリアを持ったコムギ(トウモロコシコムギ)は、暑い環境下でもその情報を敏感に感知・変換し、トウモロコシのような適応反応を引き出すことができるのではないかと期待しています。
こうした細胞質雑種の植物を作ることができれば、気候変動下でも安定して育つ作物の開発につながり、ひいては食糧問題の解決やバイオマス資源の確保にも貢献できると考えています。このプロジェクトの最終的な目標は「カーボンニュートラル」の実現です。つまり、より多くのCO₂を吸収・固定できる革新的な植物を創出することを目指しており、私たちは顕微授精法を駆使して、これまでに存在しなかった新しい穀物やバイオマス植物の開発に挑戦しています。
多様性の創出で未来の農業に変革を
私たちの研究の最大の特徴は、「遺伝的多様性の創出」にあります。実は、細胞質雑種を作ると、ひとつの組み合わせからさまざまな形質をもつ雑種が生まれます。これは、異種のミトコンドリアが組み込まれる割合・パターンに違いが生じることで起こる現象で、とても興味深いものです。多様な雑種が生まれれば、たとえばバイオマスを多く得たい場合は大型の品種を、風に強い作物が必要な場合は小型の品種を選ぶことができます。しかも、ミトコンドリアによって現れる遺伝的形質は安定して次世代にもわたって受け継がれるため、有用な形質をもつ系統が見つかれば、それを安定的に栽培することができます。
今後、地球規模での環境変動がさらに激しさを増すと予測されています。こうした変化に対応するためにも、多様な雑種の創出は非常に有用だと考えます。たとえば、水が乏しい地域や、逆に湿潤な地域、高温な地域など、それぞれの環境に最適な作物を育てることが可能になります。私たちが生み出している多様なバリエーションの中から、その土地に最も適した作物を選び出すことができるのです。このアプローチは、従来の考え方とは逆の発想です。これまではある特定の形質を付与するという方向性の育種が主でしたが、今後は、まず遺伝的多様性を大幅に拡張し、その中から環境に適応した作物を選ぶという方向にシフトしていくかもしれません。そうした意味でも、作物の遺伝的多様性をさらに広げていきたいと考えています。
【Web限定】ムーンショット型研究開発事業と並行して、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)のプログラムの一環として、イネの品種改良にも取り組んでいます。現在一般的に栽培されているイネは「栽培イネ」と呼ばれ、約1万年にわたる人為的な選抜と育種によって収量性を高めてきましたが、その過程で、野生イネが本来持っていた耐塩性、高温耐性、耐湿性、耐病性といった“たくましさ”を失ってきました。そこで私たちは、遺伝学研究所と連携し、野生イネと栽培イネの交配によって雑種受精卵を作成し、野生種の有用な遺伝資源を栽培種に導入するプロジェクトを推進しています。近年も「高温障害」が大きな課題となっているように、今後の農業には予測困難な気象変動への対応力が求められます。そうした中で、遺伝的多様性を持つ品種の開発は、持続可能な食料生産体制を構築する上で非常に価値のある取り組みだと考えています。
もっとも、こうした技術や新しい品種が社会で実際に使われるようになるまでには、まだ時間が必要です。現在は形質評価の段階にあり、実用化には年単位の時間がかかる見込みです。私としては今後も、基礎研究と応用研究の両方をバランスよく進めながら、将来的に環境問題などの社会課題に貢献できればと考えています。