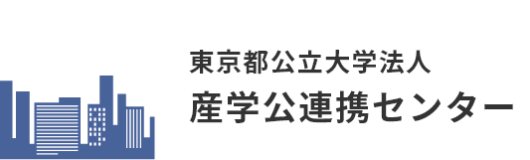写本の書き込みが語る 中世ヨーロッパの信仰と想像力
14~15世紀のイギリスで書かれた文学作品には、キリスト教の聖地がどのように描かれ、当時の人々にどう受け入れられていたのでしょうか。
中世の写本に残された読者の書き込みなどを手がかりに、600年以上前の人々の信仰や想像力の世界をひもとく研究について、人文社会学部人文学科 英語圏文化論教室の杉山ゆき助教にお話を伺いました。

杉山 ゆき 助教
SUGIYAMA Yuki
人文社会学部 人文学科
中世ヨーロッパのキリスト教徒は聖地とどのように触れ合っていたのか
「昔の人々が何を考え、何を信じ、どのように暮らしていたのかを知りたい」そう思ったとき、手がかりとなるものには、絵画や彫刻、建築物などさまざまなものがありますが、「文学」もそのひとつです。私の専門はそうした文学の研究で、14~15世紀のイギリスで書かれた宗教文学やロマンスに着目し、キリスト教の聖地・エルサレムがどのように描かれていたのか、それを人々がどのように読み解き、日々の信仰の中に取り入れていたのかを調べてきました。
エルサレムは、イエス・キリストが処刑・埋葬され、復活を遂げたとされる場所。言うまでもなく、キリスト教にとって非常に重要な場所です。しかし、14~15世紀当時、キリスト教を篤く信仰するヨーロッパ諸国は、その聖地を自分たちの影響下に置くことができずにいました。なぜなら、11世紀末以降聖地奪還を目的に行われた「十字軍の遠征」は失敗が続き、新たな遠征を始めるのも現実的ではなかったからです。その結果、エルサレムはキリスト教徒にとって物理的に簡単には訪ねられない場所となりました。そのため、教会を中心に、キリスト伝や巡礼記、十字軍戦記のようなさまざまな書物、宗教儀式を通じて人々に聖地を思い描かせることで、想像を通じて聖地を取り戻そうとする試みが行われたのです。
読書行為から「聖地回復」の取り組みと中世ヨーロッパの社会像や価値観を紐解く
そうした聖地回復の取り組みを、私は特に「読書行為」に焦点を当てて研究してきました。中でも研究対象としているのが「写本」です。写本とは、人の手で書き写した“コピー”のこと。印刷技術の黎明期にあった後期中世ヨーロッパでは、聖書や信仰の手引き、物語といった書物は、人から借りたものを書き写したり、書籍商から気に入ったものを購入したりしてテクストを集め、ある程度のテクストのまとまりができたら専門店で製本してもらうのが一般的でした。つまり、読者は大量の製本済みの本の1冊を購入するのではなく、個人の関心にあわせて転写・編纂された唯一のコピーを読んだのです。そうした写本には、書き手の癖や個性が表れます。例えば、書物の内容を深く理解するために、その書き手がどこに着目したのかメモが残されていることがあります。そのような書き込みをつぶさに見ていくことで、当時の人々が聖地をどのように捉え、信仰心を育んでいったのか、考察することができるのです。
【Web限定!当時の読書行為について解説】14~15世紀のイギリスでは、識字率はそれほど高くなかったものの、聖職者向けにラテン語で書かれたテクストが英語に翻訳されるなど、信仰を深めるための書物がより広く普及し始めた時代でした。また、特に貴族など身分の高い人々の間では、娯楽として物語を読むことが楽しまれるように。例えば、子どもに言葉を覚えさせるためにアーサー王伝説のような騎士道や宮廷風恋愛を描いた物語を読み聞かせたり、家父長が家族に宗教教育を施すために宗教文学を読み聞かせたりすることが一般的でした。
さまざまな写本が存在する中、私は、15世紀のイギリスの第2の首都にして大規模な書物流通拠点のひとつだった都市ヨークを擁する北ヨークシャーに暮らしていたロバート・ソーントンという人物の写本に注目していました。彼は騎士物語のようなロマンス、祈祷文や宗教文学書などを自ら写し2つの写本に編纂しました。「ソーントン写本」として知られるこれらの写本は大英図書館とリンカン大聖堂図書館に現在所蔵されています。ソーントン写本を精読すると、聖地への敬虔な信仰心が、時として宗教的な他者への敵対心と表裏一体となっていることが見えてきます。宗教文学の中では、イスラム教徒やユダヤ教徒がキリスト教の「敵」として描かれる例も多く、宗教的寛容が次第に薄れていく様子が読み取れます。こうした描写は、当時の社会や価値観を理解する上で、重要な示唆を与えてくれるのです。
【Web限定!文学研究の醍醐味】写本に残された書き込みを目にすると、当時の読者が注目したポイントと、現代の私が興味を持つ箇所が重なることがあります。そんな時、時空を超えて彼らと繋がれたような、不思議な喜びを覚えます。例えば、騎士道物語の写本では、どの場面に挿絵を付けるかという選択にも、当時の人々の関心が色濃く反映されています。円卓の騎士ランスロットがグィネヴィアに振られて落ち込んでいる場面や、アレクサンドロス大王が潜水艦のような乗り物で海中を探検する場面の挿絵からは、物語を楽しむ当時の人々の姿が生き生きと伝わってきます。読書が好きだった私にとって、こうした当時の読者の反応に触れることは、研究の大きな喜びとなっています。彼らが何に興味を持ち、どう感じたのかを探る過程で、人間の根源的な感性の普遍性に出会えること。それこそが、この研究の最大の魅力だと感じています。
中世の息吹を感じながら世界の研究者と交流
このような研究を深めるため、私は中世研究で高く評価されているイギリスのヨーク大学に留学しました。ヨークはかつて大宗教都市として繁栄し、中世の面影を色濃く残す街並みが今も保存されています。写本に加え、当時の考古学的な遺物や美術作品にも触れられる環境は、研究の視野を大きく広げてくれました。また、世界中から集まった学生や研究者たちと、カジュアルな研究発表から本格的な学術討論まで、さまざまな形で意見を交わすことができたのは、研究者として大きな刺激となりました。
そうした経験を踏まえ、今後の研究では、十字軍の戦略書が東方世界の物語とともに受容される過程に注目したいと考えています。実用的な戦略書が教養の一部として、あるいはある種のファンタジーとして楽しまれるようになる変遷は、中世社会の価値観や文化の変化を探るうえで非常に興味深いテーマになると感じています。
時間を自由に使える学生時代だからこそ文学や芸術品とじっくり向き合ってほしい
皆さんは最近、本を読んでいますか?
特に、古典文学や学術書、論文など、読み解くのに多少なりとも時間がかかる文章としっかり向き合えているでしょうか。こうした文章は「つまらない」「読むのが面倒くさい」と感じて、つい避けたくなるもの。しかし、ひとつの物事にたっぷりと時間を使える学生時代だからこそ、ぜひじっくりと「難易度の高い書籍や長文を読むこと」に挑戦してみてほしいです。
SNSや動画サイトなどを見ているほうが楽しい。その気持ちは分かります。しかし実は、インターネットなどに溢れている多くのコンテンツは、これまで人類が紡いできた歴史や物語の上に成り立っています。例えば、最近人気のコンテンツには、中世ヨーロッパを彷彿とさせる要素が含まれているものも多いですが、これらの作品の作者やデザイナーは、もしかすると欧州の中世時代につくられた物語や美術、建築物などから影響を受けているのかもしれません。つまり、これまで読み継がれてきた物語や、大勢の人にしたしまれてきた文化的なモノを知ることは、こうした現代の作品をより深く理解し、楽しむことに繋がるかもしれないのです。
「半年だけ」と時間を区切っても構いませんので、本や絵画、建築物、どのような形であれ文化的なものと集中して向き合う時間を作ってみてください。その経験は、いつか数十年後に振り返ったとき、人生を豊かに彩る貴重なひとときだったと感じられるはずです。