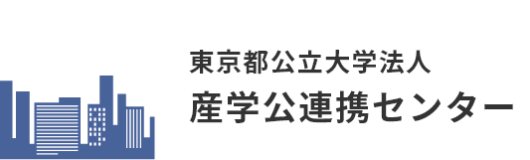数学で紐解く生物の世界
生物の進化とは、特定の遺伝子型が集団全体に蔓延し、集団全体に共通する形質の変化が見られるようになること。この進化のロジックを解明しようとする進化生態学の研究に、数理生物学の知見を活かしてアプローチする理学部生命科学科の立木佑弥助教に研究内容をお聞きしました。
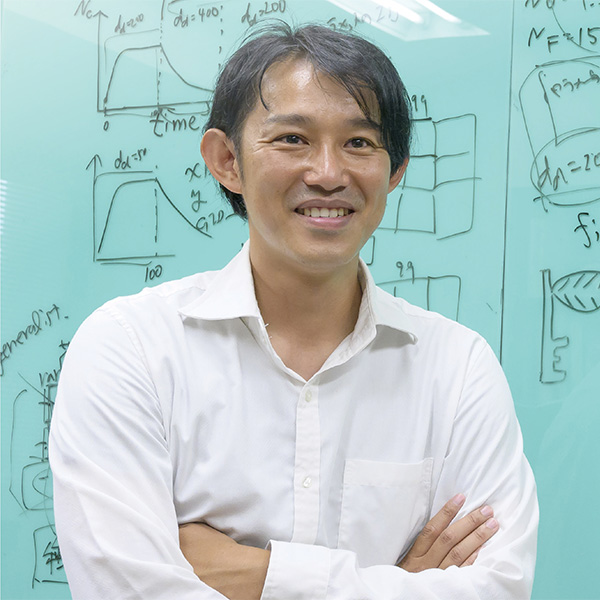
立木 佑弥 助教
TACHIKI Yuuya
理学部 生命科学科
人間以外の生き物も「美しさ」を感じている
私の専門は進化生態学。学生時代に数学を使って生物を理解する数理生物学に出合い、「美しさを感じるのは人間だけか」といった問いに向き合ったりしてきました。例えば、オスのクジャクの飾り羽は、羽の枚数が多いほどメスから交配相手として選ばれやすくなります。つまりメスには性的な魅力として映っているはずで、美しさを認識する力は、他の生物も持っているのです。
数理生物学は、こうした生物の増減や形態の変化など、多様な生命現象に共通する特徴的なデータを帰納的に抽出し、解釈を考えることからスタートします。目的は、生物の「なぜ?」を解き明かすこと。現象に潜むロジックを仮説として設定し、単純化された方程式に落とし込む「模型化」を経て、シミュレーションで検証を重ねます。私はフィールド調査を重視しながら、「データ駆動型モデリング」による「数理モデル」の確立を目指しています。
生物の生涯を左右する意思決定プロセスの謎に迫る
ニジマス、ヤマメといったサケ科の魚類には、川で生まれた後、成長とともに川にとどまるか海に向かうかを決めるものがいます。川に残れば毎年繁殖できますが、海では厳しい環境にさらされます。それでも、例えばヤマメの場合、子どものときに体が大きいと川に残ってヤマメとして生きる選択を行う一方、小さい個体は海を目指し、サクラマスへと成長を遂げて川に戻ってくるのです。そこで私の研究では、ヤマメの子どもが自らの大きさを判断する基準や、意思決定プロセスの解明に挑んでいます。
また、オタマジャクシがカエルになる「変態」のタイミングも研究しています。体が大きいオタマジャクシは早くカエルになり、小さいと遅くなる傾向がありますが、大きさと環境条件の掛け合わせによる最適なタイミングがあると考えられています。これは「リアクションノーム」と呼ばれ、実際の飼育データと数理モデルを組み合わせて、サイズとタイミングとの関係を探っています。
驚異の体内時計!タケの120年周期開花説を検証
私の研究対象には植物の進化も含まれており、そのひとつが60年周期や120年周期で開花する「タケ」です。海外から日本に移植したタケが、元々の生息地と同じタイミングで開花した事例もあり、温度をはじめとする自然環境の条件に左右されない精巧な体内時計を持つことがわかっています。私が目指すのは、120年の開花周期が最適解だといえる決定的な要因を突き止め、種によって開花周期が異なる必然性を明らかにしていきます。長周期での作用をリアルタイムで追い続けることは容易ではありませんので、数理学的な手法を駆使したシミュレーションが果たす役割は大きいといえます。
ヒトの男女比が1対1に近いのはなぜか?
ヒトの男女比がほぼ1:1であることも、実はとても不思議なことです。生物はメスが多ければ、それだけ子孫を多く残し、数が増えやすくなります。しかし、実際にはその比率にはならず、私たちの出生性比は男性がわずかに多い程度です。他の生物の例では、オス同士がメスを奪い合うことで、オスが繁殖に至るまでに死亡する確率が高く、オス同士の争いに勝つために体を大きくしようとする分、無理が生じて病気で早死にすることもあります。そのため、生まれた時点ではオスの方がわずかに多くなり、繁殖する頃にほぼ1:1になっていくと考えられるのです。では、ヒトもその他の生物も、どのようにこの合理的な最適値を導き出しているのか。生物の不思議は尽きません。
生物は不思議がいっぱいだからこそ探究したい
クジャクには派手な羽がありますが、クジャクに非常に近い種でも派手な羽を持たない種が存在するように、生物には多様な可能性があります。多様なロジックが複雑に絡み合うため予測は困難を極めます。
それでも、何が特徴や形質を分かつ境界線になっているかを解明するために、数理モデルを構築していくことが研究の醍醐味。クジャクならば、羽を美しくする要因となるデータに目星をつけ、実際に美しい羽への進化をもたらす関数の答え合わせまで行います。
研究手法の王道は、まずシンプルでスタンダードな関数を当てはめた上で、生物ごとの特徴を加えていくこと。「さもありなん」の方程式を考えることが数理モデルの基本であり、変数や条件、パラメーターを設定してシミュレーションへと移行していきます。生物には例外も多く、生態は単純ではない非線形性を示しますが、引き続き生命現象を説明するシンプルで美しい方程式を追い求めていきます。