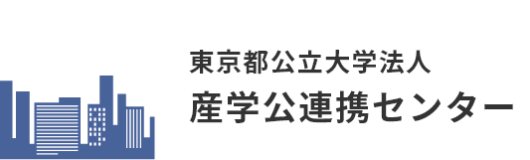語彙量は諸刃の剣。脱“紋切型”の思考で積極的な言語化を
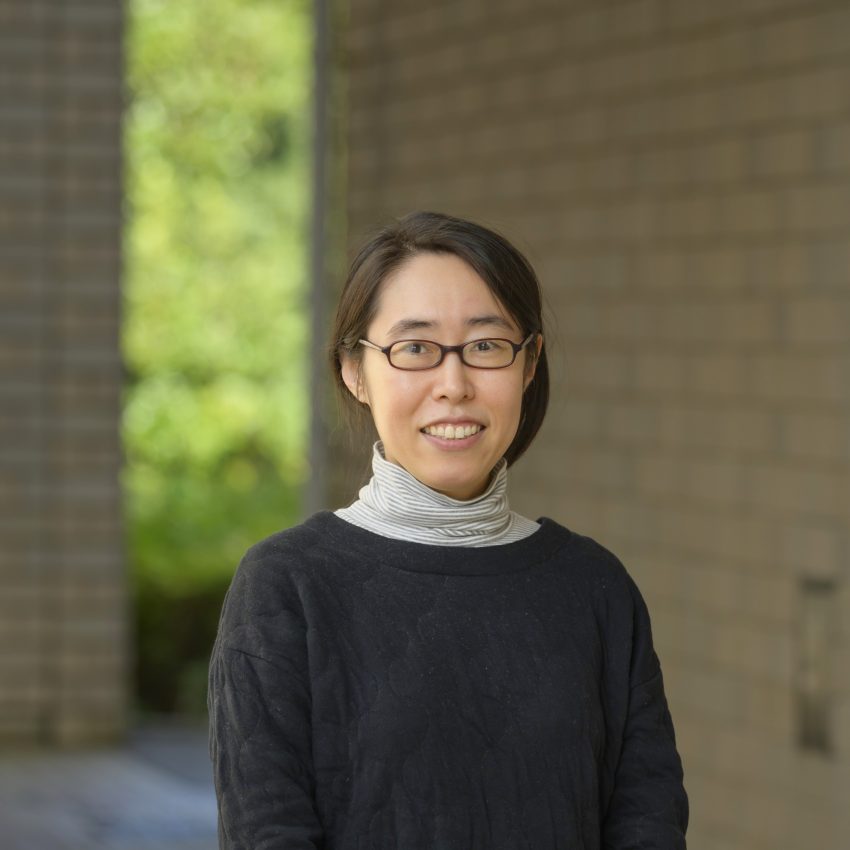
福岡 麻子 准教授
Asako Fukuoka
人文科学研究科 文化関係論専攻 ドイツ語圏文化論分野
言葉はときにノイズとなるがそれらを解放するのも言葉である
私は2004年にノーベル文学賞を受賞した作家、エルフリーデ・イェリネクの作品を中心に、オーストリア現代文学を研究しています。イェリネク作品との出会いは大学院生の頃、留学先のウィーンで観た演劇です。当時は台詞の意味も意図も理解できないほどでしたが、言葉だけではなく視覚や聴覚に訴えかけてくる世界観に魅了されました。その作品は、原作を読んでもやはり難解でしたが、そこで感じたことが、わからないことを解き明かそうとする発想やプロセス自体が、絶対的なものではないということです。
社会には複雑でわかりにくいことばかりです。解明・解決できるという前提ですべての現象に向き合い、何らかの正解を導き出そうとする道とは別の方向性があってもよいと思うのです。また、私はイェリネクの作品が「わからない」と感じましたが、では他の作品は本当に「わかった」といえるのか、「わかる」とは何なのか、「わかる」という境地は何をもって形成されるのかについて思いを巡らせました。たどり着いた見解は、人は物事を「わかろう」とする際に、類似の性質や解釈をその物事の中に見出し、知っている言葉を“紋切型”でその物事に当てはめがちだということ。そうやって自分なりに意味を再構築し、「わかった」気になって安心したいのではないかということです。深く考えて表現する前に、ときに違和感を覚えたまま短絡的に知っている言葉で片づけてしまいがちのように思います。
例えば、授業でイェリネクを読んで「哲学的」だと話す学生もいます。そうしたとき、「哲学的」という既知の言葉のもとに考えているのは実のところどんなことなのかを皆で話し合います。言葉のストックが自由な思考を阻害するノイズとなり、紋切型の思考に陥ってしまうこともあります。「女性は料理が得意」「男性は機械に強い」といった発想にしても、当然ながら絶対的なものではなく、言わば多様性とは相反する性差の“お仕着せ”に過ぎず、ある意味ではフィクション。必要なのはノイズを掻き分けて考え抜くことです。
多様な物事を“我が事”として捉え、自分で言語化してみてほしい
イェリネクの研究では、「自分で体験していないこと」を語る意味も考えさせられます。例えば東日本大震災の際、私は名古屋にいたため、地理的には「当事者」とはいえない一方で、恐怖を覚えたことは確かであり、また原発を持つ社会の一員として、「無関係」ということもできません。地理的・時間的な距離が媒介としてある中で、どこからが実体験なのか、「直接」と「間接」の線引きには難しさがあります。イェリネクは震災とその後の原発事故へのリアクションとして、『光のない』という作品を発表しました。彼女は直接的な被災者ではなく、狭義の「当事者」ではないといえますが、本人にとっては決して他人事ではなかったからこそ作品化したのです。自分で体験していないから「関係ない」と考えて何も語らなければ、いずれ忘れ去られかねない危うさは、日本国内で戦争体験を語り継ぐ活動にも通じる部分があります。何事も当事者任せにすべきではなく、考えたことをどのように言語化するかということは、誰しもにとっての課題だと思います。
言語化にはさまざまな方法があり、たとえば報道は史実・事実を無駄なく“最短距離”で的確に言語化する一方、文学はフィクションを通してしか見えない部分に光を当てることができます。また、これまで言語化されてこなかった“筆舌に尽くし難い”状況が腑に落ちる言い回しで表現されていれば、読者が新たな言葉の使い方に出会えることも文学の魅力です。その瞬間は、文化や価値観、制度、経済感覚が“異質”な海外で、それまで自分にとって当たり前だった物事が、当たり前ではなかったと感じる瞬間にも似ているもの。紋切型の思考から自らを解き放つ瞬間にもなるはずです。
 文学研究の原点は、オーストリアの作家バッハマンの『マリーナ』やドイツ人作家ゲーテの『若きウェルテルの悩み』を読んで興味を持ったことだという
文学研究の原点は、オーストリアの作家バッハマンの『マリーナ』やドイツ人作家ゲーテの『若きウェルテルの悩み』を読んで興味を持ったことだという
 コロナ禍で世界各国に足を運ぶことが難しい分、文学を通して未知の世界に飛び込んでみてほしいと福岡准教授はいう
コロナ禍で世界各国に足を運ぶことが難しい分、文学を通して未知の世界に飛び込んでみてほしいと福岡准教授はいう